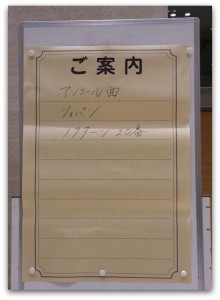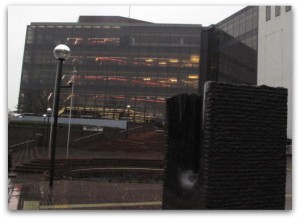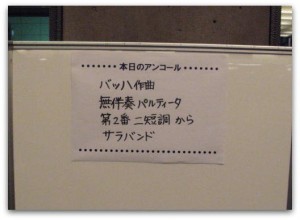一昨日の夜は、初台の東京オペラシティコンサートホールで東京フィルの定期演奏会。
前半はモーツァルトのピアノ協奏曲23番。
指揮のチョン・ミョンフン氏の弾き振りを楽しみにしていましたが、指の故障により、指揮のみに変更。
ピアノは小林愛実さんに。
小林さんのピアノは、モーツァルトのカデンツァの部分や、アンコール曲での、独特の間が印象的です。
後半はマーラーの交響曲第5番。
聴けば聴くほど、はまってしまう面白い曲ですね。
第4楽章のアダージェットは、やはりホールで実際の音の響きを聴くべき曲です。
トランペットも大活躍ですが、今日はホルンも。
前半のモーツァルトでもつくづく感じましたが、ホルンはなんとも不思議な楽器ですね。
終演後、熱心なファンの方々が拍手で、再度チョン氏のみならず、奏者の方々も再度登場して挨拶する、めずらしい事態に。
最後はステージ上からファンと握手。大人気でした。