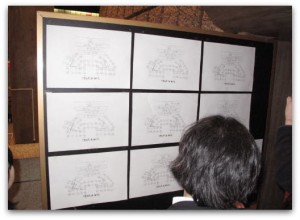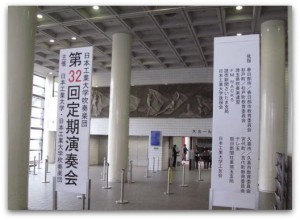日曜日にオーチャードホールで聴いたのは、井上道義指揮・東京フィルのショスタコーヴィチの交響曲第7番ハ長調「レニングラード」。
前半はハチャトリアンのバレエ音楽「ガイーヌ」第1組曲より抜粋。
演奏される機会の多い5番とは違って、7番をホールで聴くのは初めてです。
終演後、井上氏はステージ上から、客席に座っていらした指揮者の尾高忠明氏に「あなたがプログラムを変更してくれたから、今日この曲を演奏できた。ありがとう!」と。
実は、一昨年の7月、井上氏が病気療養のために、指揮は代わりに尾高忠明氏に。
その時に、尾高氏はプログラムも変更して別の曲を指揮。終演後に客席に向かって、「彼が復帰したら、本日予定だったプログラムをそのまま演奏しますから、その時をお楽しみに。」と演奏会を締めくくったのです。
会場内も、そのことを覚えている人も多数いたでしょう。
尾高氏は笑顔で応え、もちろん、場内はひときわ大きな拍手で盛り上がりました。